
経済、社会、環境の好循環を生み出し、持続可能な社会を実現する。
っていうと漠然としてますね。
「環境に配慮し、自然資源や生態系が損なわれないようにする社会を実現する」
と言った方がわかりやすいかもしれません。
人がどのようにエネルギー資源を利用してきたのか、歴史的側面からみてみましょう。

資源を効率的に循環させ、持続可能な社会を実現しながら経済成長を目指す!
新たな経済の仕組みとして「サーキュラーエコノミー」が進み始めています。
循環資源が重要な要素となりますが、鍵となるのはエネルギーの選択です。
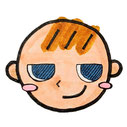
人類が最初に利用したエネルギー源といえば、「火」です。
メソポタミア文明の時代に水のエネルギー(水力)を利用するために水車が作られました。

風のエネルギーを使用する帆船も、移動手段として存在していたそうです。
やがて風車が作られることで、移動以外の動力にも風が利用できるようになりました。
18世紀までは主要なエネルギー源はこういった自然エネルギーのほか、薪、炭、鯨油などといったものが主だったようです。

この後、18世紀に入るとイギリスで石炭の利用法の改良が行われました。
1765年にジェームズ・ワットが蒸気機関の改良を行いました。
これは人類の利用できるエネルギーに革新をもたらした「産業革命」の原動力となる訳です。


時代とともに電気エネルギーの実用化が始まりました。
20世紀に入ると石炭に変わって石油が主に用いられるようになりました。

そして核燃料を利用する原子力エネルギーが実用化されたんだね。

2018年には世界のエネルギー消費量は138.6億トンに達し、石油が34%、石炭が27%、天然ガスが24%を占め、8割以上が化石燃料由来のエネルギーとなっています。
これからの人口増に対して人類はどのようにエネルギーを選択していくのか?
人類最大の目標である世界平和実現を改めて第一に願います。
